今回の問いは、「他社との違いって、そもそもどこから生まれてくるのか」です。
よく「差別化」という言葉が出てきますが、そもそも自社と他社の違いって、何なのでしょうか。
もっと言うと、そもそも「違う」って何なのでしょうか。
ビジネス書でも、平積みとか大きい通路の近くの本だと出てこないのですが、奥の書棚に行くと、抽象思考とか、〇〇の思考、みたいな本が出てきます。
ハードカバーで、300ページくらいある、重たい本がひっそりを眠っているようなテーマではあります。
でも、本来、「差別化」について、本当に考えようと思ったら、みんなと一緒の視点で「差別化」について考えていては、「差別化」することはできません。
みんなと同じ時点で、一緒になってしまいますので。
そういった視点からも、そもそも「違い」とは、どこからやってくるのかという観点から、見ていきたいと思います。
差別化とは何かを考える前に
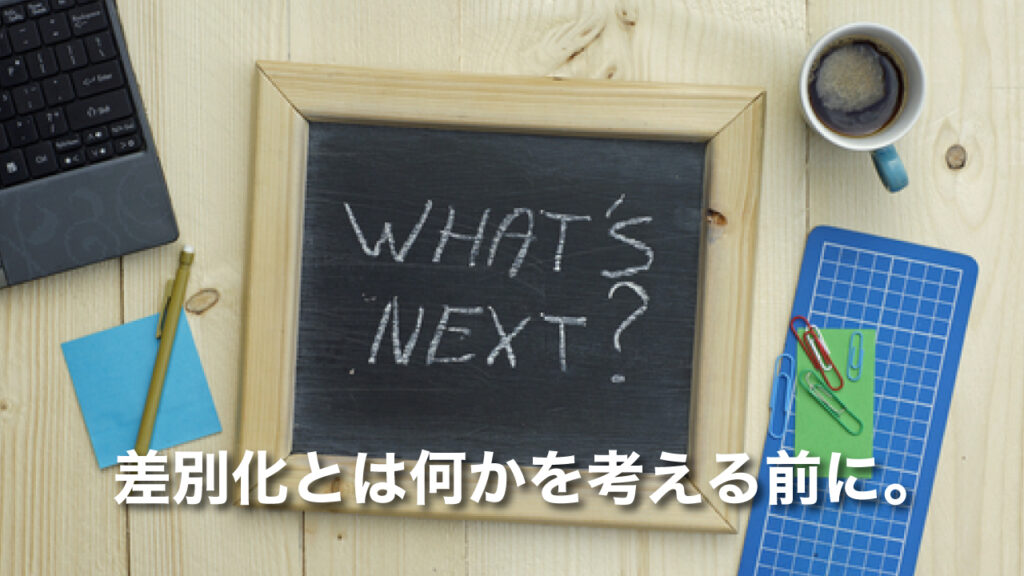
では、そもそも「違い」とは、一体何なのでしょうか。
例えば、カバンを例に考えてみましょう。
Aというカバンは1万円で、Bというカバンは5万円、Cというカバンは100万円だったとします。
ABCのカバンは、カバンとしての要素に違いはありません。
カバンとして、荷物を持ち運ぶ機能には差がないということです。
さて、では、3つのカバンは、どこに違いがあるのでしょうか。
そうですね。色や金具、皮の材質などに目を向けた方もいらっしゃるかもしれません。
もちろん、それもありですが、やはり100万円の値段をつけるとなると、よっぽどの材質であっても、なかなか難しいのではないでしょうか。
とすると、お気づきの方も多いと思いますが、「ブランド」ということになりますね。
でも、「ブランド」って、一体何なのでしょうか。
ちょっと変な話にもなりますが、「ブランド」持ってきてと言っても、持ってこられるものではないですよね。
仮に、ロゴのついたカバンを持ってきたところで、それは「ブランド」バックであって、「ブランド」そのものではありません。
では、「ブランド」とは、一体何なのでしょうか。
資本主義社会とは何かを考えてみると

いきなり経済学的な話に飛躍したわけではありません。
でも、「ブランド」そのものを考えようとすると、行き着くのは、今ある社会システムそのものに行き着きます。
なので、「ブランド」を考えるためには、どうしても資本主義社会というものが、どういうものであるか、その一端に触れる必要があります。
先ほど触れたように、そもそも「ブランド」というのは、実体がありません。
それはまるで、数学の記号のようなものです。「+=>」という記号に、実体はありませんよね。
「ブランド」も同じように、実体の無いただの記号です。
なので、ある現代思想家は、資本主義社会を「記号消費社会」と評したと言われています。
そして、記号を消費する資本主義社会に、終わりはありません。
なぜなら、記号を買うためには、別の新しい記号の生産に手を貸して、そのお金でもって、新しい記号を購入しているからです。
つまり、誰かが記号を買うと、誰かがお金を手にして、その人がまた別の誰かの生産した記号を買っていく。
こうした状況が折り重なって、資本主義社会は成り立っているために、資本主義社会に終わりはないということができるのです。
ですが、こうした世界が、差別化と何の関係があるか、分からない方も多いと思います。
その点について、次で説明しようと思います。
差別化しようとすると、どんどん似てきてしまう現象

そもそも、なぜ他と「差別化」する必要があるのでしょうか。
人間にとって、水は必要不可欠なもので、365日水を飲まない日はありません。
でも、別に蛇口をひねれば、世界で一番きれいな水が、簡単にしかも安く手に入ります。
わざわざペットボトルで、水を買う必要はありません。
日本で初めて缶のお茶が出てきた時も、同じような感想があり、最初は売れないと揶揄する声もあったようです。
でも、今では、必要とされていますよね。
だから、今になっても、缶やペットボトルのお茶が売られています。
ただ、作っているメーカーの人や、そこに関わっている人たちには悪いのですが、市販の大量生産品である缶やペットボトルのお茶の、味の違いってわかる人はいらっしゃいますか。
A社のお茶と、B社のお茶・・・何社も作っていますが、違うのはラベルだけで、同じ工場から出荷されているのではないかと思ったことはありませんか。
別に、違いのわかる人は、それはそれで人生の楽しみなので、良いかもしれません。
ただ、多くの人にとっては、それくらいのものでしかありません。
そもそも、お茶の中で、違いを出そうとしても、なかなか難しいのは目に見えています。
理由は、お茶の中で差別化しようとすればするほど、他の会社が出しているものと、どんどん似てきてしまうからです。
そして、比較ができるということは、似ているからできることでもあり、全く別のものであれば、比較の対象になりません。
なので、本当の意味で、そこから抜けようと思ったのであれば、そもそもの発想から変えていかなければ、そのカテゴリーによくある商品にしかならなくなってしまうのです。
最後に
さて、これまで「差別化」ということを考えるために、いろいろな観点から考えて参りました。
そもそも「違う」って何か。という視点から、カバンを例に、「ブランド」というものが、どういう性質のものであるか見てきました。
そして、「ブランド」は、目に見えない「記号」であり、今生きている資本主義社会は、「記号消費社会」であることに触れました。
それから、「記号消費社会」では、記号を購入するために、別の新しい記号の生産に手を貸して、お金を得て、また別の記号を購入している社会でもあることがわかりました。
そのため、こういった世界に生きていることを前提にして、「違う」という点を見出す必要があります。
ですが、違いを出そうとすればするほど、似てきてしまう現象についても、記してきました。
比較ができるということは、そもそも似ているからできることであって、その中で、差別化しようとしても、結局はどこにでもあるような、そのカテゴリーにある似たような商品の1つになってしまいます。
「違う」という記号を作るには、同じ視点に立って、同じ似たような発想がわいてくるだけでは、解決することはできません。

