会社を長く続けていくためには経営戦略が必要です。
戦略がなく、ただなんとなく経営をしているだけではいつか売上が下がったり、競合にシェアを奪われたりと会社にとっての危機が訪れる可能性があります。
しかし、どのように経営戦略を作れば良いのか分からないという方もいるでしょう。
そんな方に役立つのが3C分析です。
これはマーケティングでよく使われるフレームワークで、市場・顧客、競合、自社について詳しく分析することで、適切な会社の戦略を導き出せます。
会社の経営は自社はもちろんのこと、ライバル、消費者、景気などあらゆる要因から影響を受けます。そのため、経営戦略を考えるのであればこうした要因をしっかり分析することが欠かせません。
だからこそ3C分析は多くの企業で取り入れられています。
そこで今回は中小企業のために3C分析の具体的な手順をご紹介していきます。
3C分析を成功させるコツもご紹介するので、経営について悩み事がある、これから自社の戦略を考えていきたいという方はぜひ参考にしてくださいね。
経営戦略を決めるのに役立つ3C分析とは

3C分析は会社の経営戦略やマーケティングを考える際に使われるフレームワークです。
3Cは
Customer・・・市場・顧客
Competitor・・・競合
Company・・・自社
の3つを指します。
会社の経営にはこれらが大きく関わってくるからこそ、この3つについて分析することで、会社がどういう方針をとっていくべきなのかが明確になります。
3C分析は会社の経営を考える際の鉄板の手法で、多くの企業で取り入れられています。
3C分析の目的
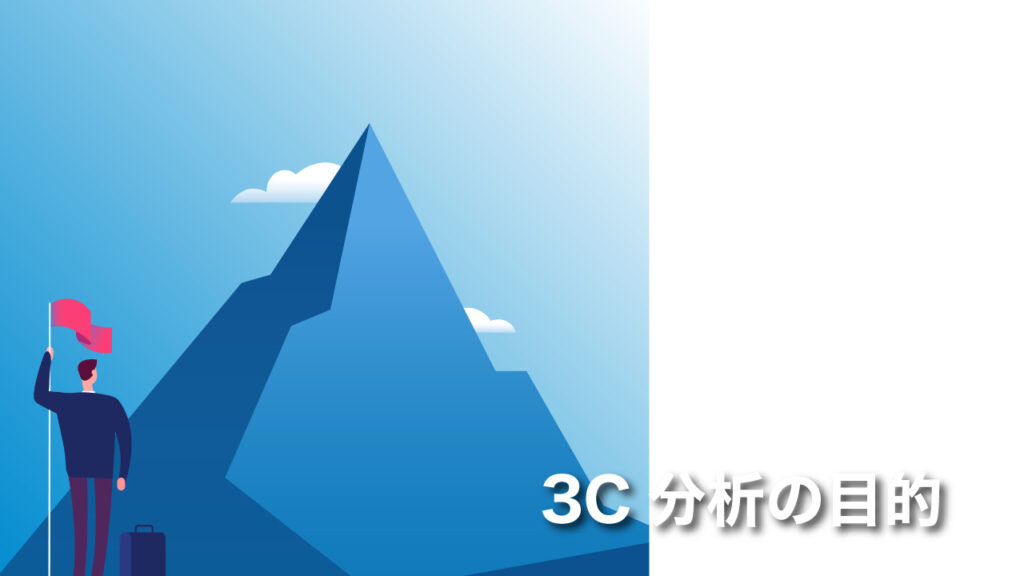
3C分析の目的の1つは企業の主要な成功要因を見つけることです。これをKey Success Factors、略してKSFと言います。
KSFは経営戦略の核になるもので、これをもとに具体的な対策や方針を決めることで、企業の成功に繋げることができます。
経営において目指すべきものがはっきりすると、資金や人材などの経営資源を適切に配分することが可能になり、効率的に戦略を進められるため、成果も出やすくなります。
Customer:市場・顧客分析の手順

ここからは具体的な3C分析の手順をご紹介していきます。まずはCustomer(市場・顧客)の分析について詳しくご説明していきましょう。
分析項目(市場)
市場では以下のような項目を分析します。
- 市場規模はどれくらいか
- 市場規模はどのように推移しているか
現在の市場の状況はもちろんのこと、これからどのように変化していくのかについても分析します。
分析項目(顧客)
顧客については以下のような項目を調べます。
- ペルソナはどんな人物か
- 見込み客はどのくらいいるか
- 購買時にはどのような意思決定プロセスが行われるか
- 消費者の購買の決め手は何か
- 顧客のニーズはどのようなものか
- どれほどの購買力があるか
このように具体的なターゲット像を分析し、さらにそのターゲットがどのように商品を購入するのかを明らかにします。
具体的な分析手順
一般的に市場・顧客分析ではマクロ分析とミクロ分析を行います。
まず、マクロ分析では景気、人口、さらに政治的状況といった直接企業に影響を及ぼすわけではないものの、間接的に影響を与えるものについて調べます。
マクロ分析ではPEST分析という手法がよく使われます。
PESTはPolitics(政治・法律)、Economy(経済)、Society(社会・文化)、Technology(技術)の4つの頭文字を取ったもので、PEST分析では自社を取り巻くこれらの重要な環境について分析します。
政治・法律は増税や政治的状況、経済なら景気や賃金、社会・文化では人口やライフスタイル、技術では新しく誕生したテクノロジーなど、それぞれの分野で自社に影響を与えそうなものについて情報を整理します。
一方でミクロ分析は自社に大きく影響を与える環境要因について分析するものです。ミクロ分析でよく使われるのはファイブフォース分析と呼ばれるものです。
この分析では
- 売り手の交渉力
- 買い手の交渉力
- 競争企業間の敵対関係
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
の5つに焦点を当てて、自社を取り巻く状況を分析します。
これらの分析結果から、顧客のニーズや購買行動など他の項目についても予測し、全体の分析結果をまとめまししょう。
Competitor:競合分析の手順

続いて競合分析についてご紹介していきます。競合は自社の売上に大きく影響を与える存在ですから、この分析も非常に重要です。
分析項目
競合分析では以下のような内容について調べます。
- どのような競合がいるか
- 売上はいくらか
- 業界でのシェアはどれくらいか
- どのような戦略で展開しているか
- どのような経営資源があるか
- なぜ成功しているのか
- 強みと弱みは何か
売上などの基本的な情報はもちろんのこと、なぜ成功しているのかといった具体的な要因についても探ります。
具体的な分析手順
競合分析ではまず競合となる会社を明確にすることから始めます。
競合は1社とは限りませんから、候補となるものはどんどん挙げ、出揃ったところで最終的にどの会社に絞って3C分析を進めていくのかを決めましょう。
市場や顧客に関する情報は公的な機関のホームページなど、入手する方法がたくさんある一方で、競合に関する情報はあまり公開されておらず、情報収集しにくいという難点があります。
そこで、企業のサイトやパンフレットを見たり、顧客や競合に出入りしている業者から競合に関する情報を収集したりと色々な手段を使うことが求められます。
情報が集まったら、上記の分析項目についてまとめ、さらには競合がどのような戦略で経営してきたのか、競合が抱えている課題は何かといった具体的なところまで掘り下げます。
このように競合分析をすることで、自社が競合とどのような差をつけられるか、どういった点で優位に立てるのかといったことが見えてきます。
Company:自社分析の手順

最後は自社分析です。市場・顧客、競合の状況を把握し、さらに自社の状態も明らかになれば、取るべき経営戦略が見えてきます。
自分の会社についてはよく分かっているつもりでも、改めてデータを見て振り返ることで意外な発見が出てくることがあります。
分析項目
自社分析では次のような項目について明らかにしていきます。
- どのような経営理念があるか
- 強みや弱みは何か
- どのような経営資源があるか
- 消費者にどのような価値を与えられるか
- 売上や顧客数はどのくらいか
- 業界でのシェアはどれくらいか
このように調査すべき項目はたくさんありますが、全て社内に情報があるため、比較的簡単に情報収集ができるでしょう。
具体的な分析手順
自社分析は調べる項目も手順も競合分析と似ています。ただし、競合に比べると分析に使える情報が豊富なので、深く分析することができるでしょう。
自社と競合の情報が出揃えば、SWOT分析をしてKSF(主要な成功要因)をはっきりさせましょう。
SWOT分析とはStrengths(強み)、Weaknesses(弱み)、Opportunities(機会)、Threats(脅威)の4つの観点から自社を分析するフレームワークで、自社の市場における優位性や課題が明確になります。
そのため、この分析を通してライバルにはない強みでアプローチしたり、逆に競争が激しい分野からは手を引いたりと、適切な経営戦略を考えることができます。
経営の方針が決まったら、自社の規模や経営資源を考慮しつつ具体的な施策に落とし込み、それを実行していくことで3C分析を生かした戦略を進めていきましょう。
3C分析を活用するために押さえるべきポイント5つ

3C分析の成果を出すためには、先ほど紹介した手順に沿ってただ取り組むだけではなく、細かい部分に注意しつつ進めていかなくてはいけません。
そこで最後に3C分析で押さえるべきポイントをまとめていきます。
十分な情報収集をする
これまで説明してきたように、3C分析は市場・顧客、競合、自社について分析することで適切な経営戦略を見つけるものです。必要な情報を集めるのは時間がかかり、骨の折れる作業ですが、十分な量の情報を集めることによって、最後に導き出される結論が正確なものになります。
情報収集にはホームページ、本、紙の資料、インタビューなど色々な方法があるので、うまく使い分けながら必要な情報を集めましょう。
短期間で終わらせる
正確な結論を導き出すために十分な量の情報を集めることが求められる一方で、3C分析は出来るだけ短時間で終わらせることもまた重要です。
なぜなら市場の動向や消費者のライフスタイルなど、3C分析で調べる項目はどんどん移り変わっていくものだからです。そのため、分析に時間をかけすぎると、経営戦略が出来上がる頃には状況が変わってしまっている可能性があります。
そこで、3C分析は丁寧に分析を行いつつ、テンポよく作業を進めるように意識しましょう。
競合や分析項目は必要に応じて取捨選択する
短期間のうちに3C分析を終わらせるコツの1つは分析項目を必要に応じて取捨選択することです。
3C分析では様々な観点から分析することで正確性の高い結論を導き出せますが、もれなく調べようとすると途方もない時間がかかります。
そこで、本当に必要なものに絞って分析を進めていくことがポイントになります。
例えば、競合分析ではいくらでもライバル企業を挙げることができる会社もあると思いますが、その全てを分析するとキリがありませんから、どうしても外せない企業に絞って進めることが大事です。
また、分析項目も重要度の高いものだけを取り上げて分析するようにしましょう。
個人の感情は入れない
3C分析で大切なことは個人の感情は入れず、客観的なデータに基づいて分析を進めていくことです。
「ライバルのここが弱ければいいな」、「市場がこう推移していけばいいな」という感情を持ちながらデータ収集をしていると、偏った情報を集めてしまいかねません。
また、本来とは違う結論を導き出してしまう可能性もあります。
そこで、3C分析をする人は個人の感情は捨てて分析に当たることが求められます。
会社の規模が大きいときは事業部ごとに行う
社内に色々な部署がある企業の場合、会社単位で3C分析を行うと、強みや弱みの把握や競合との比較が難しくなることがあります。その際は会社全体ではなく、事業部ごとに分析を行うことで対処しましょう。
まとめ
3C分析は企業の課題を見つけたり、経営戦略を決めたりするためのフレームワークで、Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つについて分析をします。
必要な情報を集めるのは非常に骨の折れる作業ですが、確かな情報を集めることによって結論の正確性も上がるため、妥協せずに行いましょう。 3C分析を通して自社の取るべき戦略を見つけ、経営改善に繋げましょう。

