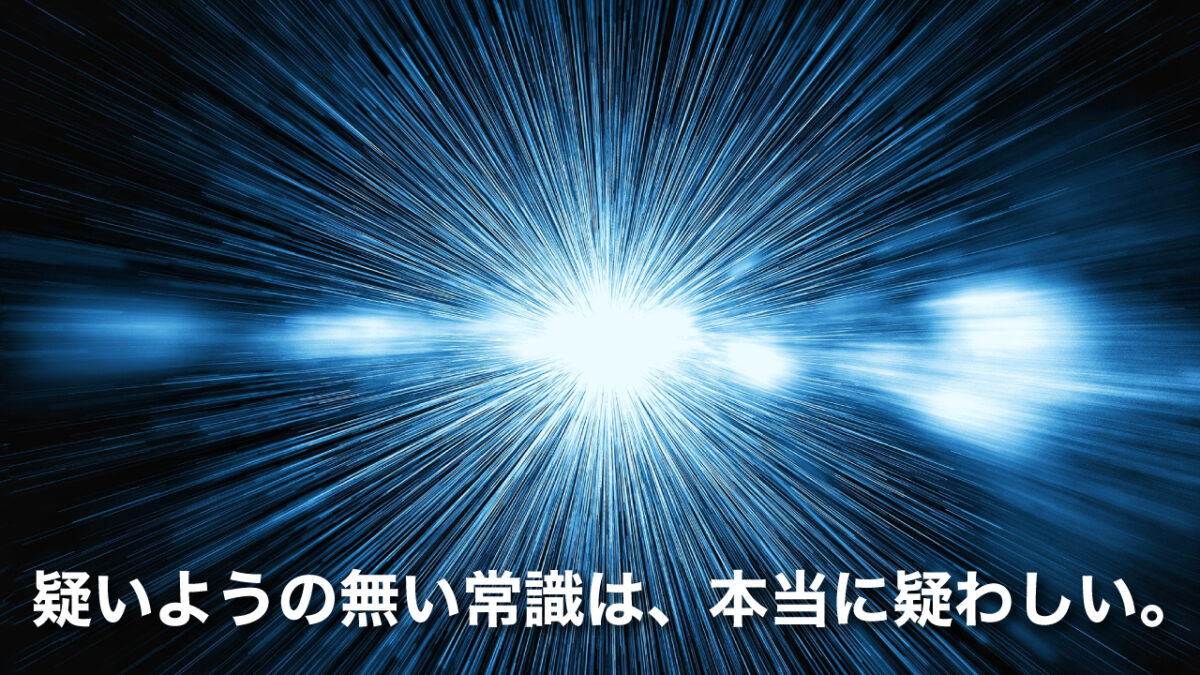はじめに
今回のテーマは、「疑いようの無い常識は、本当に疑わしい」です。
赤ちゃんの頃を思い出してほしいのですが、と言われて思い出すことのできる人は、おそらくそんなにいないと思います。
なぜならば、人の記憶は、言語を習得する過程で、定着するものだからです。
反対に、言語習得以前には、記憶というものは、事実上存在し得ないとも言えます。
では、なぜそのようなことが言えるのでしょうか。
今回のテーマは、この部分から始めていこうと思います。
言語習得以前の記憶の正体。

これはあくまでも、言語の側面から見た人間の記憶に対する考察なのですが、基本的に、赤ちゃんの頃の記憶は、すべて言葉を使えるようになってからの後付けです。
理由は、言葉を持っていないということは、赤ちゃんにとって、世界は存在していないのと同じだからです。
大人になってからの、「あれなんだけっけ?」は、物事の映像だけが浮かんでいて、それに当てはまる言葉だけを忘れてしまっています。
ですが、この場合は、その人の人生の中で、その浮かんでいる映像に対する名前を覚えたタイミングがあり、一時的にそれを忘れてしまっているだけと言えます。
ただ、赤ちゃんの時の場合は、まったく違った状態になっています。
というのも、言葉を覚えたことがなく、目の前のものが、何であるかは、その時点では把握できていないからです。
この部分を、別の角度から見てみましょう。
例えば、日本語の「木枯らし」という概念は、英語を用いる特に南国のエリアでは、全く通じないようです。
四季が無いことで、冬が存在しないため、それらのエリアの人にとっては、表現する必要のない概念と言えます。
そして、必要のない概念であるがゆえに、「木枯らし」という言葉も感覚も存在しないのです。
こうした人が、秋深い時期に日本に来て、「木枯らし」を体感したらどうなるでしょうか。
おそらく「木枯らし」という言葉も感覚も知らないため、「ただの冷たい風」にしか思えません。
「木枯らし」という概念も、言葉も、それに当たる現地の言葉が無いため、その概念を体感することができないからです。
四季が無いということは、「春一番」という言葉も概念も、無いのかもしれません。
これは、日本語が優れているという話ではなく、日本語にはなくて、外国語には存在している概念も、もちろんあります。
この場合は、今説明したことと反対で、外国の人には理解できる概念であっても、日本人には無い感覚があるということになります。
「疑いようの無い常識は、本当に疑わしい」のは、その「常識」が人それぞれ違うから。

先ほどの部分では、赤ちゃんの時の記憶という視点から、その言葉を知らないと、その概念を把握することができない、というお話をしてきました。
これを冒頭の話に当てはめて、考え直してみると、より理解が深まってくると言えます。
というのも、「疑いようの無い常識」という言葉の中に含まれている「常識」が、人によって、当てはまる概念の範囲が異なるからです。
言い換えれば、ある出来事が、人によっては常識だったり、ある人にとっては常識ではなかったりするということです。
これは、何かを批判・批評する時にも同じことが言えて、そもそもその「常識」なる感覚が、共有されていないことが原因で、食い違いが発生していることも多くあります。
これは以前お伝えした「2+3=6」も同じです。
「それ間違っているよ」と思ったとしても、その星では「+」が「×」の意味かもしれないからです。
そして、そもそも「+」が「足す」という意味であることも、もしかすると地球だけの概念であって、他の星では通用しないかもしれません。
同様に、よくよく考えてみると、「2」という記号が、「2つ」という概念を表すかどうかも、人間が暫定的に決めているだけで、今後は変わるかもしれないし、ある地域では概念が見直されるかもしれないのです。
人間が火星に移住でもするようになったら、火星での人間の常識と、地球での人間の常識は、異なったものになる可能性も否定できません。
「科学的根拠」の怪しさ。

ここまでは、言葉と記号という部分から、「疑いようの無い常識は、本当に疑わしい」ことについて、考察を加えてきました。
怪しさ満点のこの世界において、確かなものなど存在しないことがわかってきたと思いますが、これは「科学的根拠」という概念においても同じです。
そんなものは存在しません。
そもそも、本当に科学を追い求めている研究者にとって、一番恐ろしいこととは何なのでしょうか。
それは、自身の発明した概念で、世界に終止符を打ってしまうことです。
「世界の謎を解き明かしたのだから、もう生活には困らないだろう」と思う人も、もしかしたらいるかもしれません。
ですが、実際には逆です。
むしろ、自らの提唱した言説において、「例外事項(反証例)」が出てきたほうがありがたいのです。
なぜそう言えるのかというと、本当に、その分野の「世界の謎」を解き明かしてしまったら、その研究者は、もうやることがなくなってしまうからです。
自身の研究分野において、「世界の謎」が永遠に出てくるからこそ、その研究に終わりはないし、終わりがないからこそ、その研究に突き進むことができると言えます。
そして、科学を追い求める研究者は、そのことを当然知った上で、自身の研究を極めるべく、日々取り組んでいます。
「科学的」という表現や、「科学的根拠」といった振りかざしているものがあったとすれば、それは単なる現代科学におけるデータの積み上げた結果に過ぎないということです。
天気予報とかも、日夜精度を高めるべく取り組んでいると思いますが、2021年の科学では、「雨が降る確率は50%」と表現するのが精一杯です。
もちろん、それは悪いことではありません。
むしろ、「何月何日の何時何分何秒に、この地点で、10分30秒間、局地的に30ミリの強烈な雨が降ります」となったら、災害などを防ぐことにはつながりますが、
学校の運動会などで、大雨による中止の予定が、「予想外に晴れて」開催する喜びは、無くなってしまうでしょう。
今は土の校庭がどんどん減っているので、そんな心配(常識)こそ、不要なのかもしれませんが。
おわりに
さて、今回は、「疑いようの無い常識は、本当に疑わしい」というテーマで、考察を進めてきました。
「それが当然」という出来事を、いかにして引き離して、「疑いの目」を向けることができるかどうか。
この点は、今回のテーマに限らず、考えていく必要があると言えます。