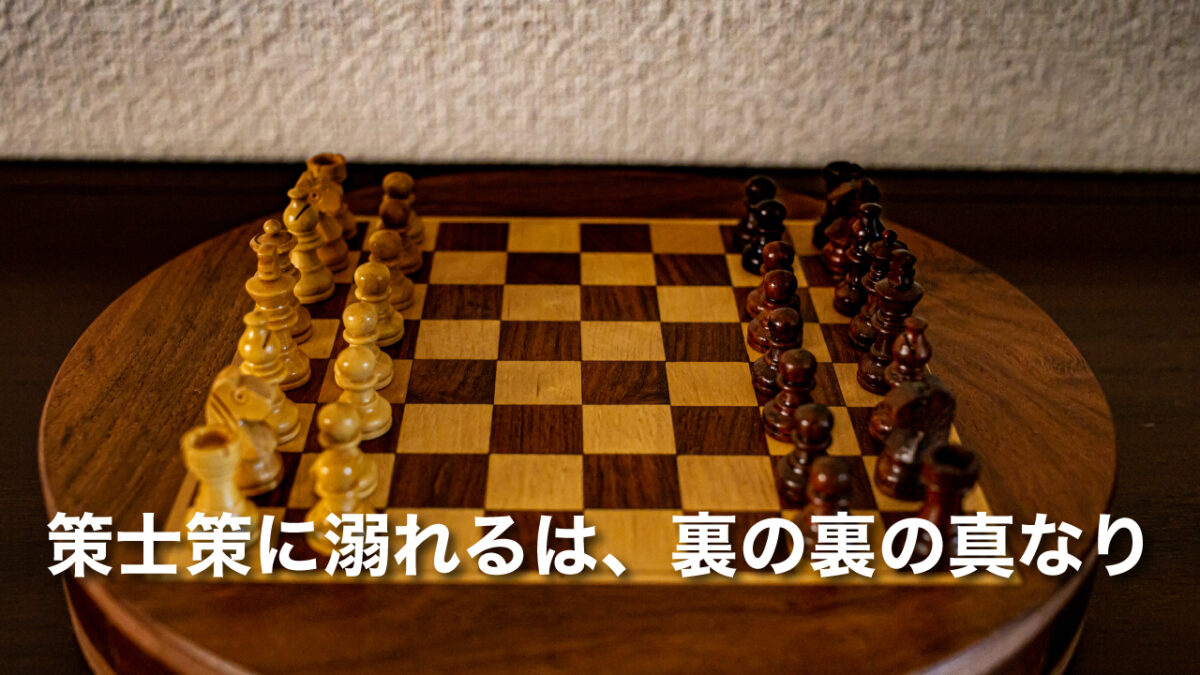はじめに
今回は、「策士策に溺れるは、裏の裏の真なり」というテーマで、記事をお送りしてきます。
先日、ある書店を散策していたのですが、気になるタイトルを見つけました。
といってもお恥ずかしながら、どんなタイトルだったか忘れてしまったので、ここには挙げることができませんが、
そのタイトルを見て、感じたことは思い出したので、その点について触れていくところから始めていきます。
言葉には、常に裏側が発生してしまう仕組みがある。

さて、どんなタイトルだったか忘れてしまった書籍の名前ですが、「人は見た目が9割」みたいな感じのタイトルでした。
ちなみに、今回お話しするテーマに、同書は全く関係ありません。
確か、「買い物の9割が無駄」みたいな感じだった気もしますが、それは横に置いておくことに致しましょう。
というのも、そもそも「その買い物」が「必要」か「不要」かという議論は、1=1と言っているようなものだからです。
どういうことか説明すると、この主張は、あくまでも主観による絶対真の命題でしか無い、ということです。
つまり、誰かにとっての正しさは、同時に、誰かの正しくなさに起因します。
しかしながら、もしそうだとして、Aという人が「A」と主張して、Aさんがそれを正しいと認識していることそのものを、誰が間違っているということができるのでしょうか。
ここに、このキャッチコピーの矛盾性というか、混沌性を醸し出していると言えます。
ちなみに、この本を出した著者も、最終的に、タイトルを決定して、出版した編集者と出版社も、すべてをわかった上で、このようなタイトルを付けて、売り出していると見えます。
なぜなら、平台に置いてある書籍ならまだしも、棚に刺さっている本の場合、背表紙のタイトルを見て、書店に来た人は、手に取るかどうかの判断を行うからです。
そのため、キャッチコピーを見た瞬間に「?」と引っかかりが持てなければ、その本を手にとってもらうことはできません。
だからこそ、「買い物の9割が無駄」というキャッチコピーは、多くの人の「?」を生み出し、手にとってもらうことができるのです。
ですが、この記事のタイトルにもあるように、冒頭で、「策士策に溺れるは、裏の裏の真なり」と書きました。
「買い物の9割が無駄」という主張をしてしまうと、ある側面において、策士が自身の術中に、ハマってしまうことに気がついたからです。
次の章では、この点について、詳しく見ていきたいと思います。
「買い物の9割が無駄」という主張の裏側。

「買い物の9割が無駄」という主張は、一見すると、目を引くタイトルです。
「そうか、買い物の9割は無駄なんだな」と思い、本を手にとって、中身を見てみる人も多いと思います。
ですが、ここで問題なのは、「買い物の9割が無駄」という主張をしている本もまた、「無駄なんじゃないか」と思われてしまうという事実です。
基本的に、世の中に売られているもので、無駄ではないものはありません。
なぜかと言うと、「生きていく上で、本当に必要なものなど、ほぼ無いから」です。
そうは言っても、住む場所は必要だし、食べ物だって必要で、着るものも必要ではないか、と思われる人もいると思います。
ですが、実際のところ、法律面での見解を無視して、単純に生物としての人間で考えると、
路上でバラックでも立てて、住めばよいですし、食べ物は森で木の実を採集したり、海に出て魚を釣ればよいのです。
着るものなどで言えば、正直なところ、大事なところが隠れていれば、それで問題ないでしょう。
結局のところ、少々汚れたり、破れたりしたくらいで、服を変えたり、賞味期限が少し過ぎたくらいで、さっさとゴミとして捨てることができるというのは、本当に必要だとは言えない何よりの証拠です。
話を本に戻すと、「買い物の9割が無駄」という主張をしている本も、その隣の本も、そのフロアの本も、すべての書店で売られている本もすべて、「買い物の9割が無駄」の9割に属するということです。
だから、「策士策に溺れるは、裏の裏の真なり」と冒頭に記したのです。
「裏の裏は表」のウソ。

さて、冒頭に記した「策士策に溺れる」は聞いたことがあると思いますが、「策士策に溺れるは、裏の裏の真なり」という言葉は耳にしたことが無いと思います。
というのも、今回の記事を作成するに当たり、勝手に作った造語だからです。
ただ、「裏の裏の真なり」という書き方をしたのには、理由があります。
それは、「裏の裏は表」という表現は、ウソだからです。
真偽で言えば、偽であり、是非であれば、非なのです。
「裏の裏」という表現をする際に、イメージとして添えられることが多いものとして、コインのような表裏のあるものであることが多いです。
ですが、そのイメージこそ、諸悪の根源であって、そもそもそのイメージが正確かどうか疑ってかからなければなりません。
なぜなら、表と裏だからといって、コインのように表裏一体とは限らず、表裏が同一空間上にあるとも限らないからです。
例えば、月夜に照らされた遠くに立っている人と、その人の影は、表裏を成しておらず、場合によっては、影が小さく、地表にあらわにならないこともあります。
つまり、月夜を浴びている人間がいても、影ができるとは限らないのです。
禅問答のような理屈ではありますが、どんな場合であれば、月夜を浴びている人間が、影を成さずにたたずむことができるのか。
自分なりに、理屈を考えてみると面白いかもしれません。
おわりに
今回は、「策士策に溺れるは、裏の裏の真なり」というテーマで、お届けして参りました。
後半は意味不明になった方もいらっしゃるかもしれませんが、
「A」という主張があったとすると、同時に「Aではない」が浮かび上がり、否定のニュアンスが立ち上がってくる、というところは、伝わったのではないでしょうか。
ここがつかめてくると、どんな主張の「A」がやってきても、「Aの影」を正確につかむことができるため、何かを判断する際の材料の1つにも成り得ます。